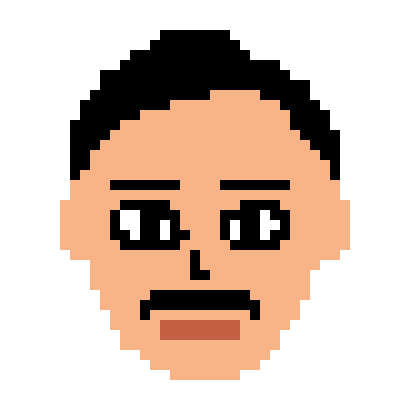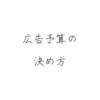【業種別】リスティング広告のCPC(クリック単価)相場を解説
「実際にクリックされた分だけしか費用が発生しない」のはリスティング広告のメリットのひとつです。それではそのクリックにはどれくらいの金額がかかるのでしょうか。
この記事ではGoogle 広告やYahoo!広告といった検索連動型広告のクリック単価について、業界/業種別の相場や調べ方について解説しています。
リスティング広告の出稿を検討している方や現在運用中でクリック単価を改善したいという人にも役立つ部分があるはずなので参考にしてみてください。
※Google 広告・Yahoo!広告で使われる用語の違いはありますが仕組みとしては非常に近いものになっています。この記事はGoogle 広告で使用されている用語に統一し記載しています。
クリック単価(CPC)をコントロールする
CPCとは「Cost Per Click」のことで、クリックあたりにかかる費用(広告費)のことです。広告が表示やクリックされることで費用が発生するリスティング広告は、だれも見ていない・クリックしていないのに費用だけが発生するということはありません。
この1クリックにかける金額(クリック単価)はGoogle広告では「クリック単価制」という入札の仕組みを利用することでコントロールが可能です。Google 広告のヘルプを使って解説していきます。
クリック単価(CPC)制は、広告のクリックに対して料金をお支払いいただくシステムで、クリック単価制のキャンペーンでは、広告のクリック 1 回に対してお支払い可能な上限額である上限クリック単価(上限 CPC)を設定します(ただし、入札単価調整や拡張 CPC を使用している場合は除きます)。
・上限クリック単価(上限 CPC)は 1 回のクリックに対して発生する料金の上限ですが、ほとんどの場合、実際の請求額はこの金額を(場合によっては大きく)下回ります。こうした 1 回のクリックに対して請求される最終的な金額を、実際の CPCと呼びます。
・広告のクリックに対して上限クリック単価(上限 CPC)を設定した場合、その額を上回る料金が請求されることはありません。
・入札単価を設定する方法としては、個別単価設定(ご自身で入札単価を設定)と自動入札機能(入札単価の設定を Google に任せて、設定した予算内でクリック数を最大化)のいずれかを選択できます。
参考記事: Google 広告 ヘルプ クリック単価(CPC)
Google広告において入札単価の設定方法を大きくふたつに分けると、クリック単価の上限を設定する「個別単価設定」と入札単価を機械学習に任せる「自動入札機能」が存在します。
「予算内で○○回のクリックを獲得したい」「クリック単価は○○円を超えないようにしたい」といった希望があれば、上限クリック単価を設定すれば実現可能です。「1クリックにかける金額は300円以下」という上限クリックを設定すれば、基本的にその金額を超えることはありません。
公式ヘルプに"実際の請求額はこの金額を(場合によっては大きく)下回ります。"と記載されているように、上限クリック単価として設定した金額がそのまま実際のクリック単価になるわけではありません。
クリック単価(CPC)が決まる仕組み
それでは実際のクリック単価や入札単価はどのように決まるのでしょうか。Google広告ヘルプ内の「実際のクリック単価」の項目が役に立ちます。
仕組み
オークション時点の広告の品質(推定クリック率、広告の関連性、ランディング ページの利便性など)、上限クリック単価、広告ランクの下限値、オークションにおける競争力、ユーザーが検索に至った背景(コンテキスト)、広告表示オプションやその他の広告フォーマットによる効果の予測をもとに、広告ランクが決定されます。広告表示オプションや広告フォーマットの効果の予測には、関連性や推定クリック率、検索結果ページでの視認性の高さといった要素が考慮されます。各広告主の広告ランクは、広告が掲載される場所のほか、広告とともに表示される広告表示オプションやその他の広告フォーマットを決めるために使用されます(また、広告や広告フォーマットが表示されるかどうかという基本的な問題も広告ランクで決定されます)。
参考記事:実際のクリック単価(CPC)
設定した上限クリック単価以外にも多くの要因があることがわかります。広告ランクについてもう少し詳しい説明をみてみます。
広告ランクは、おおまかに次の 6 つの要素で決まります。
1.入札単価 – 入札単価とは、広告のクリック 1 回に対して最大でいくらまで支払ってもいいか、広告主様が指定したものです。通常、最終的な支払い金額はこれより少なくなります。入札単価はいつでも変更できます。
2.広告とランディング ページの品質 – 広告とそのリンク先のウェブサイトがユーザーにとってどれほど有用で関連性が高いものであるかも判断基準となります。広告の品質評価の結果は、品質スコアでわかります。品質スコアは Google 広告アカウントで確認し、改善することができます。
3.広告ランクの下限値 – 常に質の高い広告を掲載するため、表示される広告が満たすべき最低限の基準を定めています。
4.オークションでの競争度 – 同じ掲載順位を競う 2 つの広告の広告ランクが同様の場合、それらが対象の広告枠を獲得するチャンスも同様となります。異なる広告主の広告のランクに違いが生じると、ランクが高い広告が掲載される可能性が高くなります。ただし、それと引き換えに、クリック単価が上昇する可能性も高くなります。
5.ユーザーが検索に至った背景(コンテキスト)- 広告オークションにおいてコンテキストは重要な要素です。広告ランクを算出する際は、ユーザーが入力した検索語句、検索時のユーザーの所在地、使用しているデバイス(例: モバイル デバイスやパソコンなど)、時刻、検索語句の性質、同じページに表示される他の広告や検索結果をはじめ、さまざまなユーザー シグナルや属性が考慮されます。
6.広告表示オプションやその他の広告フォーマットの効果 – 広告を作成する際は、サイト内の特定のページへのリンクや電話番号など、特定の情報を広告に追加できます。この機能を広告表示オプションといいます。Google 広告では、広告主様が追加した広告表示オプションやフォーマットの見込み効果も考慮されます。
参考記事: 広告の掲載順位とランクの仕組み
聞き慣れない用語が続きますが、要するに上限クリック単価でも自動入札にしろ実際のクリック単価を決定する要因となる「広告ランク」は、入札単価だけではなくランディングページや広告の品質、その他さまざまなシグナルに影響を受けるということです。
入札単価は広告スコアを決定するひとつの要因でしかなく、実際のクリック単価はそれぞれの広告主のそれぞれの入札で異なるものになるということです。
業界・業種別平均CPC(クリック単価)例
広告の配信をする前にクリック単価の相場をおおまかに把握しておきたい気持ちも当然です。
インターネットでクリック単価の相場を検索すると「業界別CPC相場」のようなデータをみかけることがあります。しかし仮に同じ業界だとしても商材やターゲットが変わればクリック単価はまったく異なるものになります。
また前の項で説明した通り、クリック単価は入札含む"広告の品質"によって決まるので、競合他社がどれくらいのクリック単価を出しているのかが自社のクリック単価を決める大きな要因となります。ということは、クリック単価(CPC)の相場を確認したければ、「業界」ではなく「自社がターゲットとしているキーワード」を確認する必要があります。
実際の単価はどれくらいなのかを、いくつかキーワードをとりあげて確認してみます。Google広告キーワードプランナーを使い各キーワードの検索回数を確認してみます。

検索キーワード「経理ソフト」に関連するキーワードです。おもに法人を対象とした経理や会計サービスで入札されるキーワードです。クリック単価は低くて200円程度、競争の激しいキーワードだと1,000円を超えることもありそうです。
下記は靴の通販に関連するキーワード例です。

キーワードに対して入札している広告主の数を相対的に示す指標である「キーワードの競合性」は非常に高いのですが、クリック単価は10円〜100円程度と先ほどに比べれば非常に安くなります。競合の数が多かったとしても各社が低い価格でしか入札しなければクリック単価は上がりません。
次はキーワード「転職サイト」に関連する例です。

転職サイトに登録する求職者を集めるためのリスティング広告の場合は、1,000円程度のクリック単価になりそうです。
「薬剤師」「医師」「看護師」などの語句を含むキーワードのクリック単価は3,000円〜10,000円になることもあり得るかもしれません。これは同じ「転職」という業界でもターゲットが変わればクリック単価も変わるわかりやすい例であり、「人材業界のクリック単価相場」を参考にする危険が理解しやすいと思います。
こちらはプログラミングスクールを検討していたり関心がある人をターゲットとしたキーワードです。

想定入札単価は500円〜1,500円程度と比較的高く、クリックから期待できる売上や利益が大きいことが予想できます。
関連記事:失敗しないリスティング広告のキーワード選びを徹底解説
CPC(クリック単価)の調べ方
知りたいのは業種や業界別のCPCではなく自サービスに関するCPCです。Google 広告公式のツールである「キーワードプランナー」を利用することでクリック単価の推定値を確認できます。

リスティング広告を出稿する際のメインキーワードとなり得るものを入力することで、その他各キーワードの月間検索回数や競合性、予想入札単価の推定が表示されます。ただキーワードプランナーは現在Google 広告を利用しているユーザー向けのツールであり、まだ広告の配信を行っていない場合には利用することができません。
そういった場合「Ubersuggest」ではおおよそのクリック単価を知ることができます。

こちらはGoogle公式のツールではありませんが、キーワードプランナーの推定入札単価と比べてみてもそこまで大きくは外れていません。
Google 広告とYahoo!広告のクリック単価
「Google 広告とYahoo!広告でクリック単価は違うのか?どちらが安いのか?」というのもよくある疑問です。結論としては、常にどちらかが安いということはなくキーワードやターゲットによってどちらが安いかは変わります。
ここで考えるべきなのが「クリック単価は安いほうがいいのか?」ということです。本当に「クリック数の獲得」が広告の目的であれば、クリック単価が安いことは目的達成のために重要です。
しかしほとんどのケースでは、「クリック数の獲得」ではなく「購入や問い合せといったコンバージョンとそこから得られる売上・利益」が広告の目的ではないでしょうか。そうであれば、クリック単価ではなく「コンバージョンにかかった費用」や「売上・利益を得るために要した費用」で媒体を比較・評価するべきです。
「クリック単価が安い=コンバージョン単価が安い」は常に正しいわけではないので、クリック単価の安い媒体やキーワードを探しても意味がないどころか逆効果になることすらありえるのです。
関連記事:結局リスティング広告はGoogleとYahoo!のどちらをやるべきか?
クリック単価を下げるためできること
クリック単価を下げることだけが目的であれば簡単です。上限クリック単価を30円に設定してインテント マッチ(旧部分一致)キーワードをいくつか追加すれば30円以下で多くのクリックを獲得できるでしょう。
そうではなく本来やりたいことは、コンバージョンを達成しやすいターゲットや対象となる検索語句はそのままでクリック単価だけを下げることです。その場合には、広告ランクに影響を与える「広告の品質」を改善するしかありません。
広告とランディングページの品質を上げるためには、
- 広告文を改善してクリック率を上げる
- 広告文とランディングページの整合性を保ち離脱を下げる
- ランディングページの改善でコンバージョン率を上げる
- ランディングページの改善で離脱を下げる
ようなことが考えられます。
Googleとしては「ユーザーの役に立つ広告を優先的に表示させたい」ので、ユーザーの悩みを解決するページの品質が高いと評価されるのは自然検索と同じです。
まとめ
リスティング広告のクリック単価相場やその前提となるクリック単価決定の仕組みについて紹介しました。
クリック単価は業界や業種ではなく、キーワード(ターゲット)に競合する他社の入札状況で半分以上が決まります。クリック単価を事前に把握したいのであれば、業界平均ではなく出稿するキーワードの入札単価を確認してください。
「予算内でできるだけ多くのクリックを獲得したい」「問い合わせや購入でなくページの訪問に意味がある」というような場合以外は、そもそもクリック単価をそこまで気にする必要がありません。クリック単価やクリック率のような一指標の変化に惑わされず、本来の目的を達成することにより注力すべきではないでしょうか。
中小企業向けリスティング広告運用代行はこちら
合同会社KAIZUKAのリスティング広告運用代行について、特徴や運用方針、支援体制、価格などをまとめました。運用代行をご検討中の方は下記のページをご覧ください。
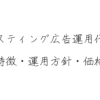
 https://magazine.kaizuka.tokyo/entry/ppcad
https://magazine.kaizuka.tokyo/entry/ppcad